私(根津孝子)がこのエッセイを書き始めてから、医療従事者(横浜在住/社会人5年目の薬剤師)である私の姪、父にとってはたった一人の孫と、よく話をするようになった。
最近のこと、彼女が想いを綴り、私に原稿を送ってきた。突然のことだ。
私は正直、その展開(原稿をもらうこと)を期待していなかったけれど、読ませてもらい、それぞれの立場で交差するその想いを改めて知り、姪に感謝した。
人は以心伝心できているつもりであっても、言葉で伝えないと案外伝わっていないのかもしれない。
最近、人と互いに話をすることの大切さをしみじみ感じている。
さて、というわけで、この連載エッセイ③、ここから先は、「大坪志穂」の原稿を掲載させてもらうことにした。
(※彼女には、「え~~~!マジで~!(汗)」と言われたけれど、叔母の説得により、最後は笑顔で了承。笑。)

届け!その想い~孫の私ができること~
祖父の癌が発覚してすぐは、家族が混乱していたように思う。骨へ転移していることで希望していた重粒子線治療などが受けられないことが分かり、絶望感が漂っていた。
これから投薬治療を受け、症状がどう変化するのかもわからない状況だったので当然のことだろう。
癌の薬を使えば副作用でどんどん弱る気がするとイメージしていたようで、悪い想像ばかりが広がっていた。
祖父の癌が発覚する以前から、家族の会話の中に「もしも自分が癌になったら……」という話が出てくることがあり、その時家族は口々に、必要以上に延命治療はせず、できれば痛みだけを取ってそのまま逝きたいと話していた。
私もその気持ちはよく理解していたけれど、しかしまだまだ諦める段階では全くない、とも思っていた。
おそらくそのことを、この時点では家族の中で私しか想像できていなかったように思う。
それほど、「癌」という音は、少なくとも癌のことを詳しく知らない人にとって、終わりを告げられているような感覚に陥らせる響きなのかもしれない。
今後できる治療法はまだたくさんあるのに、もうおしまいだという気持ちでいる家族に希望を与えることができるのは、医療従事者(薬剤師)である自分しかいないと感じていた。
そしてこれは、家族に限らず、日々接する患者さんに対しても同じことだ。
「抗がん剤」と聞くだけで、副作用に苦しみ衰弱して食べることもできず、終わってしまうイメージしか湧かず、であれば無理に積極的な治療をせず、緩和治療をするときがきたらそうしようと考える家族に、様々な選択肢があることを伝えなくてはと思った。
それにしても当時を振り返ってみると、あの時は発覚のショックで家族全員がいつもとはまるで様子が違ったように感じる。沈む人もいれば、混乱もあって言葉がきつくなる……。私自身も、諦めモードに少しいらついてきつく当たった。
ついに来たか、「仕方ない、私は冷静だよ。」と、自分たち自身に言い聞かせるように、それぞれが口を揃えていた。大人としてすんなり受け入れなければいけない事実だと全員が分かっていたからだ。また一方で、悲しみ、寂しさなどの混沌とした負の感情が、どう抑えても溢れてきたからこその強がりの言葉でもあった。
不安をぶつける場所は必然的に家族同士となり、お互いの言葉だけが強くなっていた。
表現の仕方はそれぞれ違うけれど、祖父にまだ生きていて欲しいという同じ願いを持っていたからこその、複雑な気持ちの混じり合いであったと今になってつくづく思う。
私はこれまであった家族にまつわる様々な出来事を思い出していた。熊本は震災も経験している。
震災の時、私は東京で大学生活を送っていたのだが、支え合い、励まし合った家族の力を信じたかった。

私は意を決して祖父に電話をした。癌発覚後、初めての電話だ。
癌と分かってからの祖父の様子を目で見ていなかったので、自分の言葉や言い方一つで、祖父を傷つけるリスクがあると思い、慎重に言葉を選びながら、何を伝えるか迷っていた。
電話の向こうから聞こえてきたのは、思ったより冷静ないつも通りの明るい声だった。
祖父はいつも、孫の私には心配をかけないようにしているが、あのときも、精一杯の優しさで怖さを隠していたのかもしれない。
私は悲しさをぐっとこらえ、淡々と話した。今できる治療がまだまだあること、だから諦める段階ではないということを、時間をかけて伝えた。
だがやはり、具体的な話ではないために、漠然とした不安に駆られているようだった。言える範囲は限られたが、自分が担当したことのある患者さんについて話してみた。同じ病気で余命宣告を受けても何年も先まで生きている患者さんも少なくないと。実際に私が目にしている話は、祖父にとって少しは安心材料になったようだった。
そして何より、まだ生きてほしいと伝えた。
祖父は今も一家の大黒柱で、祖父の存在そのものが家族の一体感を生み、それが揺るぎない安心感であった。そんな簡単にいなくなったら私たちはどうしたらいいの?と素直に伝えた。それが私の本音だった。
電話による気持ちの変化も少しはあったようで、徐々に祖父自身が治療に対して前向きになっていた。
自分1人の命ではない、家族がそこまで言っているのなら生きなければと思ってくれたようだ。その気持ちに続くように、周りにいる家族も今できることをやろうと、前向きになっていった。家族の気持ちが変化したあの時の安堵感は今も覚えている。
そして、あの電話から約2年半が経ったつい先日のこと、私の言葉が祖父の心に響いていたんだと感じたことがあった。
「志穂さんが俺が一家の大黒柱だけん、いなくなると困るて言わすとたい。だけんまだ死なれん」と、話していたのだ。どうやらあのときの言葉を覚えてくれているらしい。冗談混じりに祖父は笑っていたが、心はちゃんと通じていたようだ。
その日、私の目の前で祖父は大好きな旬のメロンを頬張り、「うまか~!まだ生きとったけんよかった〜!」と、満面の笑みを浮かべていた。

そうだ、祖父はまだここに生きている。
そんな屈託のない祖父の笑顔を眺めながら、こちらまで思わず笑ってしまう。これが祖父の不思議な力だ。
できることならいつまでも、そう切に願った。
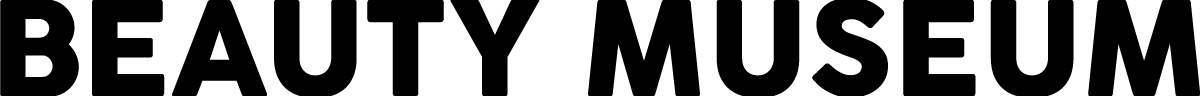


[…] (連載エッセイ③からのつづきです。) […]
[…] (連載エッセイ③はこちら) […]
[…] (連載エッセイ③はこちら) […]
[…] (連載エッセイ③はこちら) […]
[…] (連載エッセイ③はこちら) […]