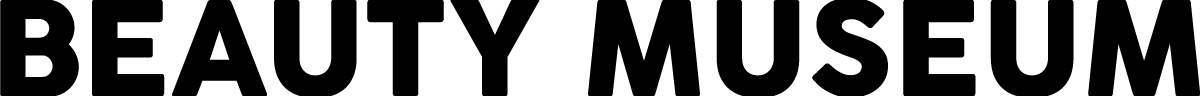2021年6月末。緩和ケアの病院同行のために、叔母と2人で帰省した。
祖父母と私はワクチンを2回打ち終わり、叔母もPCR検査を受け、万全を期した。
久しぶりに会って、みんなで夕飯を共にする。個々でそれぞれが会うことはあったが、集まったのはいつぶりであろうか。コロナ禍以前のことなので、2年以上は経っているはずだ。
時間も早かったせいか、店には私たち以外、お客さんは誰一人いなかった。
私は、L字のカウンターの角に座った。
右側に母と叔母、左側に祖父と祖母。
みんなの顔が1番よく見える場所だ。
右側では、叔母が母にちょっかいを出し、2人でケラケラ笑っている。
左側では、祖父母が何気ないことをなんとも楽しそうに話している。
5人で話すときは、笑い声が店中に響き渡る。
遂には、お店の人までも笑いに巻き込み始めた。
私は、この人たちが笑っているところを見るのが大好きだ。 とても幸せな気持ちになる、どこよりも温かい場所。
赤橙に塗られたカウンターの色が皆の顔に跳ね返り、赤らんで見えた。いつも以上に活気溢れているように感じた。
この瞬間だけは、病気のことなど忘れても、許される気さえした。

「緩和ケア」と聞くと、もう終わりを待つだけの入院というイメージが先行する。
この感覚は、私だけではないはずだろう。
今回、緩和ケアの病院を2か所訪問し、その凝り固まったイメージが、少し私の中で変化したのでここに残しておきたい。
緩和ケアとは、ガンによる痛みやつらさがひどくなった時に、それを和らげる医療のことだ。
普通の入院と違うところは、ガンをやっつける治療はしないということ。
具体的に言うと、手術や抗ガン剤をするのではなく、いかに苦痛をなくすかということに特化しているということだ。延命治療もしない。
終わりをどのように迎えたいのか、じっくりと病院のスタッフの方々にお伝えし、すり合わせをしていくのだ。
こちらの想いと、病院側が提供してくださる医療の中身が合致する場合に、患者として受け入れてくださるそうだ。この面談のあと、審議会にかけられ、入院可能かどうかの判断が下るらしい。
祖父が今の段階で、どのように今後のことを考えているのか。
「できるだけ家族全員に同じように話を聞かせたいものですから、連れてきました。」
祖父は私たちを先生方に紹介しながらそう言った。
改めて祖父の想いを聞き、ここで自分たちの中に落とし込んでいく。
2つ、どちらの病院にも共通していたのは、患者の意向が最優先ということ。
在宅で、痛みのコントロールをしたければ、家で緩和ケアを受けることもできる。
入院にてケアを受けたいのなら、お試しで入院して、どんな場所で治療を受けるのか実際に事前に体感することもできるそうだ。
体のどこの部分のガンなのか、その患者の病状それぞれに合った専門の医師と、他の医療スタッフがチームになって、治療方針を考えてくれる。
また、一度入院して体調が安定したら家に戻るという、この往来も許されているという。
ここにお世話になったら入院しっぱなしということでもないらしい。つまり、緩和ケア=終わり、ではない。私は少し緩和ケアのことを誤解していたようだ。
たしかに終わりは近いといえど、祖父の意向に沿って、臨機応変に対応してくださる体制が、そこには十分に整っていた。
「なるだけ家庭にいて、最後の短い期間をここにお世話になりたいんです」
祖父はギリギリまで、人生で1番長い時間を過ごした家に身を置きたいようだ。
これをまず念頭において、家族と、医療スタッフの皆さんで一つずつ確認すべき項目を押さえていった。
祖父の前に、先生から一枚の紙が差し出される。
残りの時間が短くなったときに、どのように命を選択するか、というチェックシートのようなものだ。

今の段階での意向をここにいる全員で統一させていく。
まず、ガンをやっつける治療はしないということ。
今後、心臓マッサージ、人工呼吸などはせず、自然な状態に任せるということ。
脱水になったら点滴をしてもいいということ。これは、あくまでも延命という意味ではなく、脱水だと患者がつらく感じるからという理由だ。
このような項目を1つひとつゆっくりと確認した。
そして、終わりをどこで迎えたいかということ。
家、できれば家、できれば病院、病院の、4択だった。
祖父は、病院の文字に丸をつけた。
祖母に、家で介護をさせて、大変な思いを背負わせたくないのだと先生に伝えていた。
「あた、俺がしかぶっとしゃがな大変ばいた。(俺がお漏らししたら大変だよ。)」
と、祖母に言って笑わせていたが、最後まで迷惑をかけたくないという祖父の気遣いだった。
そして最後に、認知症やせん妄(頭の働きが下がって、よく分からないことを言ったり、暴れたりぼんやりしたりすること)が始まったとき、誰の意向を尊重するかということ。1番本人の気持ちを分かり得るのはだれか。きっと、本人だったらこう言うと思うので、この治療をして欲しい、もしくは、もう治療をおしまいにするようにと、最後に判断する人は誰かという問いだ。
「この人はですね、長年連れ添いまして、私の1番の理解者ですたい。」
祖母を指しながら、祖父は先生に説明する。
自分が最後の意思決定をしますという証明に、祖母は、直筆でサインをしなければならなかった。
祖父を中心にして、右サイドに祖母と私、左サイドに母と叔母が座り、対面に先生方が座っていた。
そのため、祖母のサインを、私は1番近くで見守った。
祖母が自分の名前を書くのを今まで幾度となく見てきたが、このときのサインは今までで1番酷で、苦しかった。
祖父の終わりを否が応でも考えなければならない時間だった。
祖母にとって、人生の大半を一緒に過ごした祖父がいなくなることが悲しいし、隣で生きて欲しいと思うのにも関わらず、本人の1番の理解者である自分が、自ら最後の判断を下さなければならない。それを想像して、サインをしているのであろう。
隣にいる祖母の、鼻水をすする音が、かすかに聞こえる。
私の目に映る祖母の文字も、涙で曇った。
右サイドはこんな状態にも関わらず、祖父を含めた左サイドはこんなところでもまた冗談を言い合っていた。
うちの家族が賑やかすぎて、うるさいからって審議会で落とされちゃうぞ!と叔母が言い、母と祖父が笑っている。こんなときだって、やっぱりうちの家族らしい。変にバランスがうまく保たれていて、右サイドの私たちまでふと笑ってしまう、いつものパターンだ。
このようにして、祖父の理想の最後の病院が見つかった。これから色々なことを試しながら、準備をしていくこととする。

羽田に戻る飛行機に乗る時間が迫ってきた。
母の運転で空港へ向かう道の途中。車窓からは、阿蘇の山々の中に9つの白い風車が縦に並んでいるのが見えた。薄曇りなのに遠くまで見えて、今日は珍しいねと母とぼーっと眺めていた。
次にあの風車を見るときは、私はどんな気持ちだろう。祖父はどうしているだろうか。今と変わっていないといいな。爽やかで広大な景色とは裏腹に、少し怖くなった。
またねと笑って母に手を振り搭乗する。
祖父母の近くにいてくれてありがとう、よろしくね、私もちゃんと関東で頑張るから、という気持ちを込めて。