
【回想1※連載エッセイ①×根津孝子からの続き】 2018年12月。父のガン発覚。
愛犬の死はもう近いことはわかっていた。しかし状況はどうあれ、ここまで15年以上、私は愛犬と楽しい時間、そして時にはとても苦しい時間も一緒に過ごしてきた。そう、まさに相方だった。はっきり言ってしまえば、夫も子どももいない、社会の役に立つことなど何もしていない私にとって、生きている意味って何だろう?と考えた時、この愛犬のために生きているようなもんだな、と、いつも思っていた。
熊本へ行かなければならない一週間先まで、その命がもつかどうかもわからない状況だったけれど、できることなら、自分できちんと最後を見届けたかった。
愛犬の症状が急変したのは、私が熊本へ行く日の二日前のことだった…。
日ごろから私の行動や言葉を理解してくれている犬だったのだが、その日は、熊本の家族との電話のやりとりも多く、私がいつもの様子と少し違うと感じていたのかもしれない。そろそろ準備をしなければと、スーツケースを部屋に引っ張り出した日の夜のことだった。それまでは、ほぼ一日中寝たきりだったのだが、まるで最後の力を振り絞ったようにすっくと立ち、弱々しくではあったが、部屋をうろうろと歩き始めた。
時間にすると、ほんの30秒くらいだったと思う。最後に向かった先は、病気がひどくなってからは使っていなかった、お気に入りの自分のベッドだった。
そのベッドは私のパソコン机の横にあって、だいたい私は家にいるとそこに座っているのだが、私と愛犬がともに一番長い時間を過ごした場所である。
力尽きたようにそのベッドに横たわると、すぐに呼吸が荒くなり、30秒くらいすると、今度は呼吸が細くなって、そのまま静かに呼吸が止まった。
私は、その一部始終を見守り、最後を見届けた。何度も何度も「ありがとう」と言いながら……。反応はなかったけれど、その声は届いていたと思う。最後に「キュン」と小さく鳴いた。
その時私は、ほんとうに、死ぬ時ってあっけないもんだな、と思った。
「あなたの邪魔にならないように、この辺で逝きます。さようなら。今度はお父さんのこと、ちゃんとしてあげて下さい。」と言われているようなタイミングで逝ってしまった……。
果たして私はいい飼い主だったであろうか?と自問したけれど答えは出なかった。ただ、犬が元気な時にもっと一緒にたくさん遊び、楽しい時間をもっともっと一緒に過ごしておけばよかったと後悔した。

看病って何だろう?と考えた時、その答えは難しいのだが、できれば、残される人も納得できるかたちで最後を見送ることができたなら、その方がいい。
今の私は、父の闘病を見守り、自分ができることはできるだけ都合をつけながら過ごすようにしているのだが、多分それは、父のためと言いながら、実のところ自分が後悔しないためなのかもしれない、いや間違いなくそうだ。もっとこうしてあげていれば、という気持ちを残したくないのだ。そしてそれでもきっと残ってしまうのだろう。
そして、愛犬の死の二日後、熊本へ向かった。
この時期の父の症状(主に、頻尿)は、今振り返っても、これまでで一番ひどくて、本人も表面的には明るく振舞ってはいたものの、これから先、この症状はどうなっていくのだろうかと、とても不安がっていた。
私は熊本空港へ降り立ったその足で両親、姉と合流し、4人でそれまでお世話になったかかりつけ医と検査病院の2か所へ出向き、これまでのお礼と、ここから先の治療は、A病院での治療を希望する旨を伝え、紹介状を書いてもらうようお願いをした。
前述もしたが、家族はセカンドオピニオンや転院をすることに後ろめたい気持ちがあったので、結果、その場面では殆ど私が一人で話をし、段取りをする形になってしまった。まぁ、そのために熊本へ行ったのだから当然なのだけれど。
文章にすると、その流れがこんなふうに数行でまとまり、とてもあっさりとしたものになる。実際、とてもあっさりと終わった。
私にとっては、そのかかりつけ病院や先生の対応は予想通りのものだったが、両親や姉にとっては、少し驚きだったようだ。それが東京に住む私と熊本に住む家族の感覚の違いなのだろうか?家族には、「先生に話をしてもらってほっとした」と言われたのだけれど、その感覚が未だに私にはピンとこない。なぜならば、別に私は特別なことを言ったとも、したとも思っていないからだ。でもこのことで家族を安心させることができたのならば、バタバタではあったけれど、行った甲斐があったというものだ。
この時(12月中旬)まではまだ、“前立腺ガンの疑い”だったのだが、A病院での検査の予約が12月の26日にとれたので、一旦東京に戻った私は、その間、この先の治療についていろいろ調べていた。
父自身も、A病院での検査結果次第では、鹿児島の指宿の病院で受けることができる「陽子線治療」や佐賀の鳥栖の病院で受けられる「重粒子線治療」へ行って治療を受ける気でいた。身体への負担が少なく、前立腺のガンには特に効果があると言われている治療だ。父の友人にこの治療を受けた人がいたので、直接その様子を聞くことができたこともあって、根治するイメージが膨らみ、少し気持ちが晴れた様子だった。
私は私で直接病院に問い合わせをし、ガンがどのような段階であれば、「陽子線治療」や「重粒子線治療」を受けられるのかを把握した。
そうして迎えた12月28日。Å病院での精密検査とその結果を教えてもらう初めて診察の日だ。何にせよ、設備の整った大きな病院というのは、検査をしたその日のうちに結果がわかるというのがとても有難い。
その日、私と母は朝から病院に同行し、父の検査に付き添った。
「血液検査」「尿検査」に始まり、「レントゲン」「MRI」「骨シンチ」など、あらゆる検査をした。
経験したことのある人も多いと思うが、検査や検査結果を待っている時間というのは本当に何ともいえない嫌な時間である。しかも、既によくない症状も出ているので、結果がいいわけがないのだ。じゃあ、どれくらい悪いのか、その悪いレベルを知るための検査結果を待っている時間というのは、言葉では言い表せないくらい嫌な時間であった。
父の全ての検査が終わり、夕方、姉も仕事終わりで病院にかけつけ、家族四人、待合室で名前を呼ばれるのを待った……。
年末。2018年もあと数日で終わろうとしている。
大きな病院の大きな自動扉から時々待合室に流れ込む風はとても冷たくて、窓の外をみると、もう真っ暗だった。
私は「今年はほんと、いい年ではなかったな……」とぼんやり思った。
一人、また一人と、診察室に呼ばれ、広い待合室は私たち家族以外、誰もいなくなった。その日、最後の患者だった。
名前が呼ばれ、四人で診察室に入る。私は少し息苦しさを覚えるくらいドキドキしていた。
父は正真正銘の前立腺ガンだった……。
しかも既に骨に転移していた。
その時点で、「陽子線治療」や「重粒子線治療」ができないことを父本人も家族も悟った。転移があると受けられない治療なのだ。その時初めて会った先生からは、転移があるので手術もできないと言われた。じゃあ何ができるのか?それは、ホルモン療法と抗がん剤による治療ということだった。
なかなか先生の話が頭に入ってこなかったけれど、ぼんやりする意識の中で、とにかくメモをとらなくてはと思い、手帳を広げてメモをとった。
一通り今後の治療方針などの説明を受け、ひとまず待合室に戻り、家族四人、肩を寄せ合うように椅子に座った。
私は、この時父が静かな口調でポツリと言った言葉を生涯忘れないと思う。
「こぎゃんもんたいな……」
これは熊本の方言だが、標準語にすると、「こんなもんなんだな……」という感じであろう。
この時の父のこの一言にはいろいろな意味がきっとあって、「ガンの告知をされた時の気持はこんな感じなんだな」とか、「人の命はこんなふうにして終わりに向かっていくのか」とか、本当に複雑な心境の中で絞り出した一言だったと察する。
父は人並外れた明るい男だ。でも、この時ばかりは顔を赤らめて涙ぐんでいた。その表情が今もずっと私の脳裏に焼き付いている。

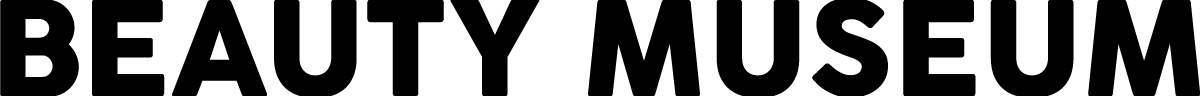


[…] (連載エッセイ②はこちら) […]
[…] (連載エッセイ②はこちら) […]
[…] (連載エッセイ②はこちら) […]
[…] (連載エッセイ②はこちら) […]
[…] (連載エッセイ②はこちら) […]
[…] (連載エッセイ②はこちら) […]