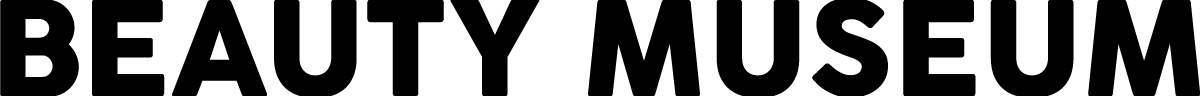ここ最近、祖父が亡くなるまでの闘病の話を、3人から聞いた。
私が見てないことを、苦しみながら伝えてくれた。
祖父の滑舌は次第に悪くなり、亡くなる1週間前くらいから徐々に聞き取りにくくなっていった。それは私も感じていて、電話で聞き取れた最後の会話が、「おばあに電話してやって」だった。
ご飯が本当に食べられなくなったのは、この1ヶ月くらいだそうだ。
痩せるのが目に見えて分かって、身体は骨張ってきた。自分でも、とにかく人に会いたくないとしきりに言っていたらしい。
身長は私より20cmほど高いが、亡くなる間際の体重は私より軽かった。
毎日自分で体重、血圧、脈拍などを記録し、まめに体調を見ていたらしい。
そんな痩せた祖父の身体を見ていると、介助する側も、グッと起き上がらせるのが怖くて、壊れ物のように優しく触れていたそうだ。
叔母は自分の腕を祖父に持たせて、引っ張らせて起き上がらせていた。
母は、全身を使って頭から抱えて、起き上がらせていたそうだ。
そんな状態でも、最後の、亡くなる日までずっと、洗顔は自分でするし、トイレにも自分で行っていたそうだ。オムツも、一度も汚さなかった。
洗面所に立っていることが難しくなってきて、洗面台の前に椅子を置いていた。
そこに座り、顔を洗って、その後は洗面台に腕を置いてしばらく休憩していたそうだ。
そして落ち着いてから、よし、と言って立ち上がり、ベッドに戻っていた。
自分は下の世話もしてない、何もできなかったと、叔母は言っていたが、たくさんのことをしたくれたことを、祖父も、私たちみんなもよく分かっている。
迷惑をかけたくない、自力でやるんだという、祖父の意志が強く、本当にすごい人だった。
それでも思うように動けなくてイライラすることもあり、祖母に当たっていたそうだ。「一番当たりやすかったっだろね。そして、最後にはごめんなって言わすとよ。」
生きたい、動きたい。その思いとは反対に、身体はどんどんいうことを聞かなくなる。そのもどかしさから、何かに当たるしかなかったけれど、一番近くにいる祖母を傷つけてしまう。「ごめんな」と謝るその祖父の心は全て、祖母に届いていた。
祖父は、最後までカッコつけしいなところがあったと祖母は言う。今までも、入れ歯を洗うのも恥ずかしがったそうで、祖母にも入れ歯のお掃除を見せたがらなかったそうだ。「あっちに行っときなっせ」と言ったり、背中を向けて掃除したりして、隠していたらしい。
身体を拭いてもらうのも、祖母には全身させるが、「全部はあただけだけんな」と言いながら、母や叔母、看護師さんにすら、背中などの表面部分だけしか拭かせなかったそうだ。
亡くなる3日前、母が1人で行った時が一番辛そうで、癌による痛みが強かったそうだ。左の肩から腕にかけてが痛くて、ベッドに横になっても痛い、起き上がっても痛いと。
母に、揉んでくれ、と頼み、揉んでもらってしばらくは良さそうだったけどやっぱり痛くて、でも、揉まなくても痛い。あちこち態勢を変えては、「どがんもならんな(どうしようもできないな)」と、呟いていたらしい。それが、面会時間の3時間ずっとだったそうだ。
痛い痛いと、騒ぐのではなく、じっと目を閉じて堪えていた。
それでも、テレビに映るプロ野球中継をチラッと見ながら、「ピッチャーがいかんな」などと言って、テレビに対する集中力は、今までと変わらなかったらしい。腕を揉み、心配する母をよそに、テレビを見る頭はしっかりしていたそうだ。
こんなことを思うのはよくないかもしれないけど、これからどうなるんだろう、どこまで弱って、どんな様子になるんだろうと、想像もつかなくて、とても怖かったそうだ。
亡くなる2日前には、母と祖母でお見舞いに行き、その時は前日より気分が良さそうだったらしい。「今日はよかごた(今日は調子がいいみたいだ)」と、言いながら、私が近々引っ越す予定の部屋の写真を見て笑っていたらしい。
私がこうして自立して、生活できていることをとても喜び、安心していたそうだ。
そして亡くなる前日、面会の時間が17時までと決められていた。
そのルールを破ってはいけないと、真面目に守った祖母と叔母。
お見舞いを終え、部屋から出るときのさよならは、いつものさよならと違ったと祖母は言った。
祖父は、祖母と繋いだその手を、ギュッギュッと指で強く握っては、声には出さずとも「行きなすな、行きなすな(行くな、行かないで)」
と言っているようだったそうだ。
もしもあれが亡くなる前日だと知っていたら、コロナのためのルールを守って、1日2人だけの面会、17時ぴったりに出るなんてことしなかったよね、と話していた。
また、亡くなる日の朝、祖父は叔母に電話をかけてきたそうだ。
「志穂はいつ帰るとかい?いつかい?」と。待ってくれていた。
「いま何時かい?」
まだ朝なのに、もう昼かと思ったと、日にちの感覚、時間の感覚が少し鈍くなっているように聞こえたそうだ。
【ここから先は、祖母と叔母が辛い中、私達に伝えてくれた、祖父の最後の瞬間ついて書きます。叔母は思い出すのも、文字にするのも苦しいと思うので、本人がエッセイにするかわかりませんが、とにかく私がこのとき聞いた話を書きます。これを私に話してくれたことについての重みを感じ、残しておくべきなのではないかと思って書きますので、辛い方はこの先の部分は読み飛ばしてくださいね。】
お見舞い行けば、いつも笑顔だったらしい。
「部屋に入ると、こっちば見てから、二コーって笑わすとよ」
祖母はそのニコーっという笑顔の話をたくさんしていた。よほど、嬉しく、印象に残っていたのだろう。
最後の日、その、ニコーっがなかったそうだ。いつもと違うなという感じだったと祖母は言った。
具合が悪いのかな〜と思いながら、祖父に頼まれていた用事を済ませてきたよと言っても、無言で頷くだけだった。
小さな声で、うん、と言ったようにも見えたけど、ほぼ声は聞こえない。目を瞑って、小さくコクンと首を動かしたそうだ。
そこから数分の間にみるみる様子が変わったらしい。
呼吸が荒くなって、叔母が急いで看護師さんを呼びに行った。
祖父の黒目が上を向いて、またしばらくすると、正面に戻ってきたらしい。こっちを見ているのかなと思ったけど、意識はもう、こちらには向いてないように見えたと。
荒い呼吸の間隔が、少しずつ空いていって、息が苦しそうな表情をしたらしい。
息をしたいけど、できないような感じだったそうだ。
祖母は、そのときの祖父の身振りを見せてくれたのだけれど、頭の上で、何かを追い払うように、手を動かしていた。
「お父さん!呼吸の練習したじゃない!ほら、一緒に呼吸ばしましょう!」
と、祖母が手を握りながら語りかけたけど、もう分かっていないようだった。
海に溺れるような、呼吸したいけど苦しいような感じなのではないかと、叔母は言っていた。
でもそれも、1分くらいの時間の話で、あっという間だったと。最後は目を自分で瞑っていったそうだ。
祖母がしきりに言っていたのは、握っていた手が湿ってきていたということ。
「ジュクジュクになってきてね。タオルでも間に合わないくらい。」
祖母も、叔母も、人の死を目の当たりにしたことはなく、何が起こっているのか、よく分からないまま、あっという間だったと言っていた。
叔母は手首の脈を取っていて、それもどんどん小さくなり、なくなっていった。
祖母が握ったその手も、爪のほうから色が変わっていった。
母の到着を待っていた。でも着いたその頃には動かなくなっていたそうだ。
祖母は、今まで生きてきて、母があんなに泣き叫んでいるのを見たのはこの時が初めてだったと、のちに私に言った。
叔母「私ね、みんなで海に行ったときなんかにみせる、ヒャッフーって裏声で言いながら、一番はしゃいでた、ああいうお父さんが大好きだったんだよね。なんかさ、たまに子供みたいなときあるじゃん。誰よりも楽しんでてさ。大好きだったんだよ。でもね、今はあの、最後の辛そうな顔と姿しか思い出せなくてさ。あのはしゃいでたお父さん、どんな顔だったか、今思い出せないんだよね。そんな自分が今、すごく嫌。」
怖かったよね。と、叔母と祖母が話す。
そのときの姿しか思い出せない叔母は、私が見たこともない程に辛そうで、
「怖かった、今急に話したくなった。」と、弱々しく言った。
こうやって話してくれたこの話の重さを、ここに記す。
私が一日早く熊本に帰ることなく、そんな祖父を見ないまま、元気な頃の姿と、今の穏やかな顔を覚えていられるなら、これでよかったと、3人に言われた。
祖母は自分の両親のときも、姉兄のときも、死に目には会えていない。
「お父さんだけだもんね。目の前で逝ってしまったのは。人生で一番きつかった。」と呟いていた。
亡くなる当日も、面会開始の時間が決められていたのだけれど、その時間まで、祖父は待っていたのではないかと振り返る。祖母と叔母が到着し、安心したのだろうか。
母の到着の後しばらくしてから、医師が時計を見て、亡くなった時刻が静かに告げられた。
その時刻は、母の誕生日、3月24日と全く同じ数字、3時24分(午後)だった。
「私の誕生日と同じ数字だ…」と、母は言っていたそうだ。
祖父は、祖母と叔母の到着を待ち、立ち会えなかった母の誕生日の時刻に旅立った。
そして、その日にちは孫の私の誕生日(1月19日)と、数字の並びが全く同じ、11月9日だった。
間に合わなかった母と私を、数字にまでして残した。祖父の存在が、私たちの人生に刻まれた。
祖父が亡くなった直後、空には大きな虹が2本かかっていたのだそうだ。
こんなことは滅多にないと、看護師さんたちも、それを眺めてとても驚いていたらしい。
空は晴れているのに、霧のような雨が降り、太陽の光に照らされた雨がキラキラと輝き、幻想的でとても美しかったのだそうだ。
祖母は、一瞬雪かと思ったと話していた。
祖父は最後の最後まで伝説を残した。