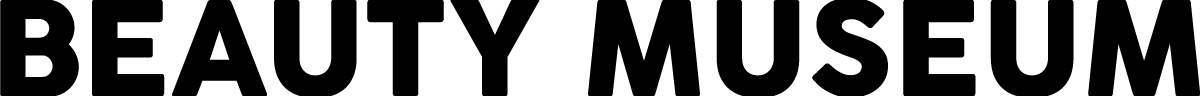祖父の身体が、この世から無くなってしまう。
最後に顔を見て、棺をお花でいっぱいにした。
生前によく被っていた帽子、チーム孝二Tシャツを2枚、手紙を入れて、
ありがとう、ありがとう、と何度も伝えた。
祖母「もうちょっと、待っててくださいね。こちらを片付けてから、私も向かいます。あたの隣に、私の席ば空けとってくださいね。」と話しかけていた。
祖父の顔は、触ると冷たくて固かったけど、まだここにいる、と思った。
形が無くなってしまうのがとても嫌だった。
祖父の棺が火葬場に入れられてしまう。
分厚い扉の奥に吸い込まれて行く。
閉められてしまった扉の前に祖母が立ち、その後ろに母、叔母と続いていた。
私はその扉と、両手を合わせる三人の背中をじっと見つめた。
この最後の光景を、一生忘れてはいけないと思った。目に焼き付けておきたかった。
祖母「お父さん、ありがとうございました。これからは、家族一丸となって頑張りますので、見守っていてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう…」
分厚い扉の向こうの祖父に向かってそう言いながら、祖母は火葬のボタンを自らの手で押した。炉に火が灯った。
このときの気持ちを、祖母はのちにこう語った。
自分が何としてでも押さなければ。こんなに辛い思いを娘二人にはさせられない、と思ったそうだ。
いなくなってほしくない。そう思うけど、自ら押さなければいけないあのボタンは、本当に酷で、こんなにも辛いものかと。
祖父は、生きることにおいて、歩みを止めるのを嫌がった。
その生き方が現れていたのが、治療方法の選択だ。抗がん剤治療のための入院はせず、ホルモン療法にしか手を出さなかった。
ホルモン療法だけをやりながら、仕事を続けていた。
入院をして時間が止まってしまうのなら、癌の細胞を叩き潰すことよりも、外に出て仕事や自分の好きなことをやるということを優先したのだ。そうやって、最後まで自分らしく生きていたかった。
止まるということが怖かったのかもしれないねと、家族が話していた。
確かに、立ち止まって、病と正面から向き合うということが、怖かったのかもしれない。
これでよかったと、私も思う。
最後まで祖父が祖父らしくあるためには、この選択がベストだった。
もし自分が死ぬ間際になったとき、自分だったら泣くし、お別れの遺書とか書き始めてたかもな、と母と叔母が振り返る。
祖父は、俺は絶対泣かん、といつも言っていたそうだ。本当に、最後まで泣かなかった。
まだ生きる気でいて、よくなるつもりでいた。
人生、もうほどほどでいいやという気持ちはなく、まだ生きたい人だった。
生きるつもりで、今後の予定もびっしり埋めていたそうだ。
ギリギリまで仕事をして生き抜き、最後まで自分らしくいて、家族に見守られて旅立った祖父はきっと、幸せな人生だったと、今頃笑っているのだろう。